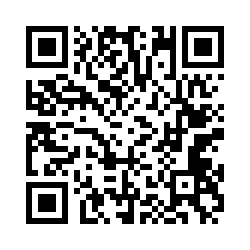仙台・オンライン・子育ての悩み・不登校・引きもこり・アドラー心理学
アドラー東北は不登校などの子育ての悩みや親子関係悪化のお悩みをアドラー心理学で解決に導く各種セミナーを開催しています。
いじめと不登校
いじめをきっかけに不登校に

不登校のみならずいじめも急増している昨今の学校現場ですが、いじめがきっかけで不登校になるというケースも当然のことながら増えているようです。
いじめにしても不登校にしても学校側が把握している数は半分にも満たないというのが現実ではないでしょうか。
自分の子どもさんが学校で何があったのか?お子さんが正直に自分の気持ちを親に話せる関係、これからのことを話し合える親子関係になっているかどうかが、問題解決のカギになると思っています。
親子関係が良好であれば、お子さんは自分の気持ちを正直に話してくれますが、そうでないと「いじめ」ということについても「不登校」ということについても、何もわからないまま親が迷い続けるという事態になります。
一体子どもさんに何が起きていて、どういう気持ちでいるのか、それがはっきりわかることがまず最初です。
たぶん~ではないか、大体~らしい、という把握ではケアはできません。まずはお子さんとの関係を見直し構築しなおすことが大事なのです。
そうして初めて対応が可能になります。お子さんとの関係は今どうなっておられるでしょうか?なんでも話せる関係になっておられますか?
もしそうでないのでしたら一刻も早く親子関係の見直しをしていかれることをご提案したいと思っております。
いじめはなぜ起きるのか?把握しにくいのか?

いじめの背景に考えられるもの
いじめはなぜ起きるのか?なぜ把握しにくいのか?
学校という閉鎖的な空間で、勝ち負けや上下関係といった人間関係の枠組みの中で起きやすいと感じています。
子ども同士が争って勝つか負けるかを競うような環境では強者が弱者をいじめるという構図は起きやすいのではないでしょうか。
また何らかの子どもの不全感がそれを埋める方法として「いじめ」という選択肢が取られることもあると思います。不全感とは、満たされない何らかの思いと言えばいいでしょうか。
自分が大事にされていない、自分は取るに足りない存在だと感じているなど、何らかの環境的要因、生育要因でそういう気持ちになっているケースもあると思います。
そのはけ口として「いじめ」という方法がとられるということもあると考えております。
相手を貶めいじめることで自分の不全感を埋めようとするということです。いずれにしても「いじめ」という方法では、その不全感はなくなりません。
双方が不幸になるだけです。一刻も早い発見がいじめのエスカレートを止める方法であることには変わりがありません。
いじめが把握しにくいのは、いじめる側が上手に隠れてやるからです。大人の目につきにくいところで、目についてもそうとわからないようにやるということが、現状の把握をしにくくなっています。
ここでも問われるのは教師と生徒の関係で「何でも話せる関係になっているかどうか」です。普段の関係がいざというときのブレーキになると思います。
いじめと不登校の関係をアドラー心理学で読み解く

アドラー心理学の目的論でいじめがきっかけで不登校になった場合を考えると対応が見えてくる
いじめが把握しにくい理由はアドラー心理学の認知論で考えると説明がつきます。
私たちはそれぞれがそれぞれのとらえ方で起こった出来事をとらえると考えるのが認知論です。
同じ出来事を見ても「どう意味づけるのか」は個人で違うのです。
いじめにあっている子が「これはいじめだ」と訴えたとしても、ほかの人もそう捉えるとは限らないということです。
誰かにとっての「いじめ」が誰かにとっての「悪ふざけ」にしか見えない可能性は多分にありますし「じゃれている」ようにしか見えないこともある。
アドラー心理学で考えると客観的に「いじめかどうか」を判断するのは無理であると思われます。なぜなら私たちはほぼ主観で生きていると考えるのがアドラー心理学の認知論・基本前提だからです。主観でしかとらえられないものを把握して「いじめだ」と認定するにはとても時間がかかりますから、その間にいじめられている当事者が追い詰められていくという事態は容易に考えられます。
ですからお子さんの訴え、もしくは周りからの訴えがあった場合には、まず事態把握の前に当事者のお子さんの安全確保を最優先にすることが必要になると考えたほうがいいでしょう。
それでは、もしもいじめがきっかけで不登校になったという場合には、学校へ行かないという事態をアドラー心理学ではどうとらえたらいいのかについて考えてみましょう。
学校でいじめがあるということは、お子さんにとって学校は「危険な場所であり安全が確保されない」と感じているということになります。
したがって「安全確保」がお子さんの学校へ行かない目的ということになるでしょう。自分の身を守るために「学校へ行かない」という選択をしているのです。これは当然と言えます。
もしもどうしても「学校へ行ってほしい」のであれば学校で「いじめという危険を回避する措置」が取られていることが必要になります。そうでなければ「危険」だとわかっているところへお子さんは決して足を向けようとしないでしょう。
安全が確保できないのであれば行かせないという選択肢もあると思います。学校側がいじめを認めないなどのケースがありますので、まずはお子さんの安全確保を第一に考え、学習の機会などはほかにゆだねることも考えていかなければなりません。
できることならば学校と協力して「登校の安全」を保障できる環境になれば一番いいのですが、現実問題としてなかなか難しいこともあるでしょう。
親と教師の関係が良好であれば、可能性がないわけではありません。ここでも普段の関係がものを言うのです。
いじめと不登校⁻現時点での対応まとめ
- 親と子が普段から何でも話し合える関係になっていること
- 担任教師と親が何でも話せる関係になっていること
- いじめられている子どもの訴えを最優先に対応すること
- いじめが発覚したら事実関係の把握よりもまず先に速やかに子どもの安全を確保すること
- 学校での安全確保について学校と話し合い対応策を考えること
- 安全が確保されにくいのであれば、学校へ行かないという選択肢もありえるということ
ごあいさつ

高橋直子
現在不登校体験者の声を動画配信中
お子さんの問題で悩んでおられる親御さんのご相談に乗って早15年になりました。たくさんの方たちが笑顔を取り戻していくことを自分の糧としてアドラー子育てを普及し続けています。
資格
- ヒューマン・ギルド社認定SMILEリーダー
- 同ELMトレーナー
- 日本支援助言士協会認定・コミュニティカウンセラー
- 日本ブリーフセラピー協会認定・ブリーフコーチ・エキスパート
- 日本アドラー心理学協会認定・マスタープラクティショナー
- 日本メンタルケア学会認定・メンタルケア心理士、メンタルケアカウンセラー

参加したかったけどあきらめていたアドラー東北の講座に参加できるオンライン
オンライン個別相談会
平日・午前・午後・夜の相談受付中
詳細はここをクリック
子育て講座SMILE
アドラー子育てといえばSMILE,テキストに沿って基本となる子どもとの向き合い方・態度・技術をじっくり学ぶことができます。月1回4回コース
2023年7月から四回コ―スで開催予定です。
マンツーマンで自分の悩みに沿ってピンポイントで解決策がわかり、同時にアドラー子育て・対人関係法が学べる全国初のアドラー心理学講座ー設定自由の4回コース、空いていればいつでもスタート可
1回の受講料が8000円とお財布に優しい4回コース